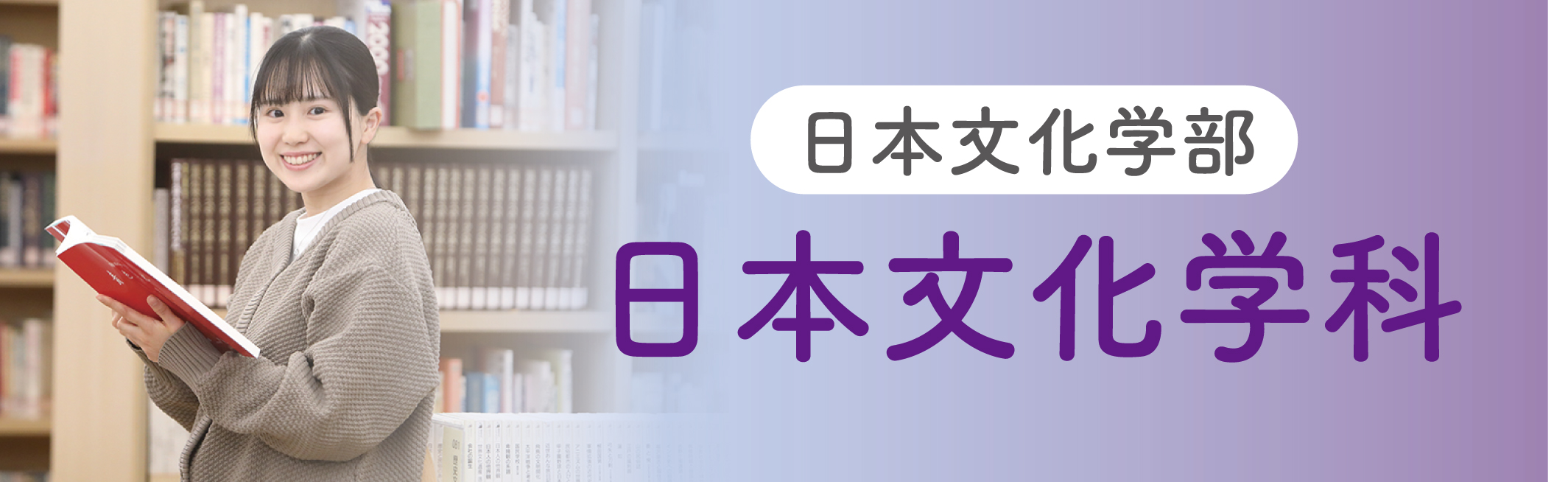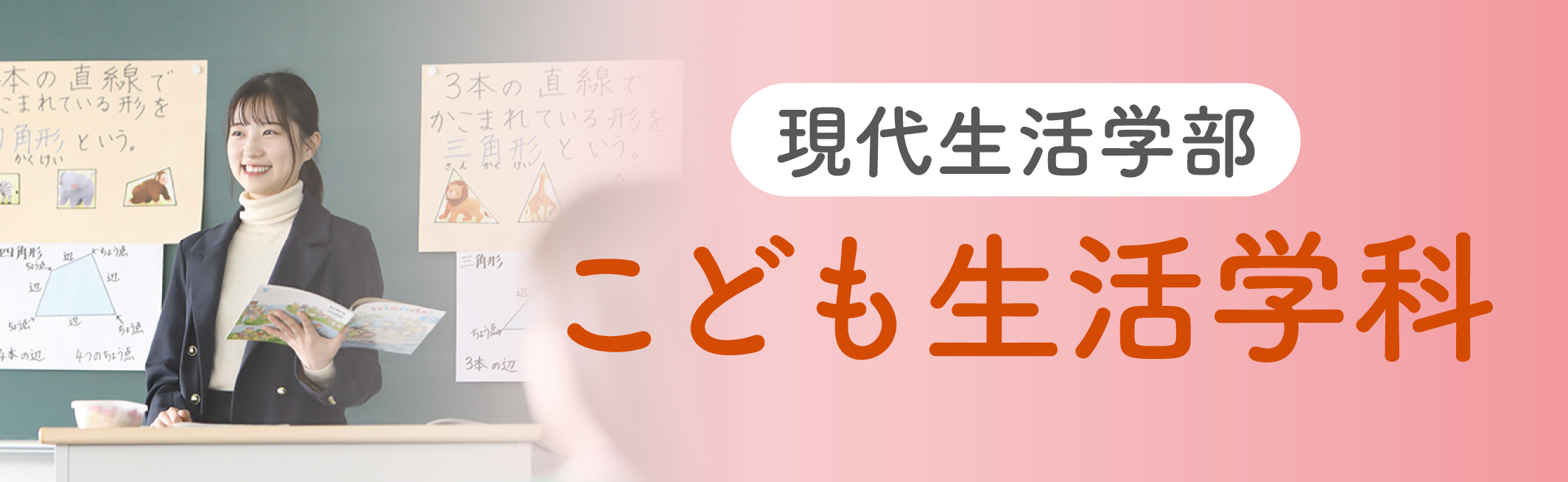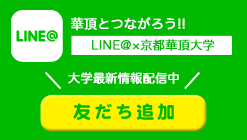教員紹介【西川 由紀子 教授】
| 教員名 | 西川 由紀子 (にしかわ ゆきこ) |
|---|---|
| 職名 | 教授 |
| 学歴 | 京都大学大学院教育学研究科博士後期課程教育学専攻単位修得学修退学 |
| 学位 | 教育学修士 |
| 担当教科 |
幼児理解 保育内容(言葉) 教職論(幼・小) 発達心理学(幼・小) 保育内容総論 乳児保育Ⅰ 幼児と言葉 卒業演習(論文を含む。) 保育実習指導Ⅰ 保育実習指導Ⅱ 保育実習Ⅰ(保育所) 保育実習Ⅱ |
| 専攻・専門分野 | 発達心理学/保育学 【保有免許・資格】 中学校・高等学校教諭免許(国語科) 臨床発達心理士 |
| 研究テーマ・内容 | 乳幼児のコミュニケーション能力の発達 自称詞をどのように使い分けているかなどを手がかりに、自我の発達を明らかにしようとしている。また、コミュニケーションの道具としてのことばの獲得が不十分な時期に、集団保育に起こる「かみつき」についても、その原因や防止のための対策などを考え、子どもたちの保育園での生活がここちよいものとなるよう研究を続けている。 \こういう研究・授業をしています/ 保育士や幼稚園教諭になるために必要な教科(発達心理学、乳児保育、幼児理解、保育内容(言葉)など)を担当しています。 研究としては、保育園での子どもたちと先生のかかわりを実際に見学したり、話を聞いたりすることで、子どもの様子を知り、子どもの発達と保育者の役割を考えています。今は、乳児に見られる「かみつき」を減らすために、どんな工夫ができるかを保育園の先生方と話し合い、分析を進めています。 |
| 所属学会 | 日本発達心理学会/日本保育学会/日本教育心理学会 |
| 学外活動 | 社会福祉法人きらら福祉会理事 |
| 研究業績:著書 |
「新版 「かみつき」をなくすために 子どももおとなも安心な毎日を」単著 令和6(2024)年 かもがわ出版 「かかわりあって育つ子どもたち 2歳から5歳の発達と保育」単著 平成25(2023)年 かもがわ出版 「「かみつき」をなくすために Part2 おとなの仲間づくりを考える」単著 平成21年 かもがわ出版 「子どもの思いにこころをよせて 0・1・2歳児の発達」単著 平成15年 かもがわ出版 「私たちは生きる 災害から子どもたちの命を守るために」 共著 令和5(2023)年 新読書社 P131-136. 「文学で育ちあう子どもたち 絵本・あそび・劇」共著 令和3(2021)年 新読書社 P39-41.100-102.103-106. 「新版・教育と保育のための発達診断下 発達診断の視点と方法」共著 令和2(2020)年 全障研出版部 P75-97. 「新・育ちあう乳幼児心理学」共著 令和元(2019)年 有斐閣 共著 P268-284. 112-113. 「教職教養講座第9巻 発達と学習」共著 平成29(2017)年 協同出版 P69-89. 「新・保育士養成講座第6巻 保育の心理学」共著 平成23(2011)年 ミネルヴァ書房 P52-60. 「育児のなかでの臨床発達支援(臨床発達心理学・理論と実際②)」共著 平成23(2011)年 ミネルヴァ書房 p114-121. 「保育のきほん 2・3歳児」共著 平成22(2010)年 ちいさいなかま社 P6-23. 「保育実践のまなざし 戦後保育実践記録の60年」共著 平成22(2010)年 かもがわ出版 P45-46.P154-155.P182-187.P210-211. 「教育と保育のための発達診断」 共著 平成21(2009)年 全障研出版部 PP66-82. 「保育の質と保育内容 保育者の専門性とは何か(保育の理論と実践講座第2巻)」共著 平成21(2009)年 新日本出版社 P61-70. 「保育のきほん ゼロ・1歳児」共著 平成21(2009)年 ちいさいなかま社 P6-23. 「イチャモン研究会 学校と保護者のいい関係づくりへ」共著 平成21(2009)年 ミネルヴァ書房 P32-43. 「保育所給食と子どものゆたかな育ち」共著 平成21(2009)年 かもがわ出版 P49-58. 「保育実践と発達研究が出会うとき まるごととらえる子どもと生活」 共著 平成18(2006)年 P115-129. 「保育小辞典」共著 平成16(2006)年 大月書店 「「かみつき」をなくすために 保育をどう見直すか」共著 平成16(2006)年 かもがわ出版 「実践に学ぶ保育計画のつくり方・いかし方」共著 平成16(2004) 年 ひとなる書房 P183.199. 「子育てブックス 泣く」共著 平成16(2004)年 草土文化 p12.18.28.34.41.47.66.87.106-110 「テキスト乳児保育」共著 平成16(2004)年フォーラム P73-93. 「3歳児 (シリーズ 子どもと保育)」平成15(2003)年 かもがわ出版 P114-122. 「小学5年生の心理」 共著 平成11(2000)年 大日本図書 P91-118. 「1歳児 (シリーズ 子どもと保育)」共著 平成11(1999)年 あゆみ出版 p172-177. 「子どもと絵本の学校」共著 平成10(1998)年 ほるぷ出版 p367-376. |
| 研究業績:論文 |
・保育園の主任の負担を軽減するために -負担感はどこから来るのか? 単著 令和3(2021)年 保育情報No.540.p115-117 ・保育園における「かみつき」と保育制度の変化との関連-21年間の保育実践報告の分析から- 単著 平成29(2017)年 心理科学第38巻第2号p40-50 ・乳幼児期における自発的あそびにみられる子ども同士のかかわりの展開 単著 平成29年 (2017)障害者問題研究45-2.p2-9 ・女子学生の自称詞の使い分け-わたし・うち・名前- 単著 平成23(2011)年 京都華頂大学・華頂短期大学研究紀要 第56号p91-99 ・子どもにとっての絵本の絵の役割-絵本「はじめてのおつかい」のおはなしつくりのデータ分析 単著 平成19(2007)年 立命館文学第599号 p62-70 ・幼児期から青年期にかけての好き嫌いの変遷と食事指導 ―「楽しく食べる」ことの大切さに注目して- 単著 平成17(2005)年 華頂短期大学研究紀要第50号 p65-77 ・クラス集団に規定された自称詞の使い分け-オレって言ったらヒゲがはえるんやで- 単著 平成15(2003)年 華頂短期大学研究紀要第48号p155-167) ・子どもの自称詞の使い分け:「オレ」という自称詞に着目して 単著 発達心理学研究第14巻第1号 p25-38 ・5歳児女児は自称詞をどのように使っているか?-「うち」使用ブームに着目して- 単著 平成14(2002)年 華頂短期大学研究紀要第47号 p88-101 ・幼児の絵本選択に影響を与えているものは何か 単著 平成12(2000)年 立命館教育科学プロジェクトシリーズⅩⅣ(AI)p39-47 ・子どもたちは本をどのように楽しんでいるか:「ズッコケ3人組」シリーズの魅力 単著 平成10(1998)年 華頂短期大学研究紀要 第43号p82-90 ・幼児の物語産出における「語り」の様式 単著 平成7(1995)年 華頂短期大学研究紀要第40号 p124-p133 ・幼児期における男性語・女性語の認識の発達 単著 平成7(1995)年 華頂短期大学研究紀要第40号 p128-138. ・幼児期における印象深い絵本体験に関する一考察・・短大生を対象とした質問紙調査に基づいて・・ 単著 平成4(1992) 華頂短期大学研究紀要第37号 p55-p68 ・子どもは舞台の上での姿を「見られる」ことをどのように意識しているのか?・・生活発表会のビデオ分析を通して・・ 単著 平成4(1992)年 乳幼児保育研究第16号 p57-62. ・劇あそび・劇ごっこにおける幼児の物語理解・・「おもしろさ」の所在をめぐって・・ 単著 平成2(1990)年 ディスコースプロセス研究第2巻2号 p55-62. ・戦前保育問題研究会における「幼児童話」研究に関する一考察 単著 平成2(1990)年 京都大学教育学部教育指導・教育課程研究室研究論集 p102-108. ・「保育の手帳」保育案研究委員会作成の保育案に関する一考察 単著 平成2(1990)年 関西教育学会紀要第14号 p128-132. ・幼児期後半における絵本理解の発達と絵本指導 単著 昭和59(1984)年 乳幼児保育研究第10号 p30-51. |
| メッセージ | 保育園や幼稚園は、子どもたちが保護者の元から離れて、自分で人間関係をつくっていく場です。ひとりひとりが、自分の気持ちをうまく伝え、友だちの思いにこころをよせることができるように援助していく保育者の役割は、とても大きいと思います。そのために必要な学びを、この大学で得ていただきたいと思っています。 |