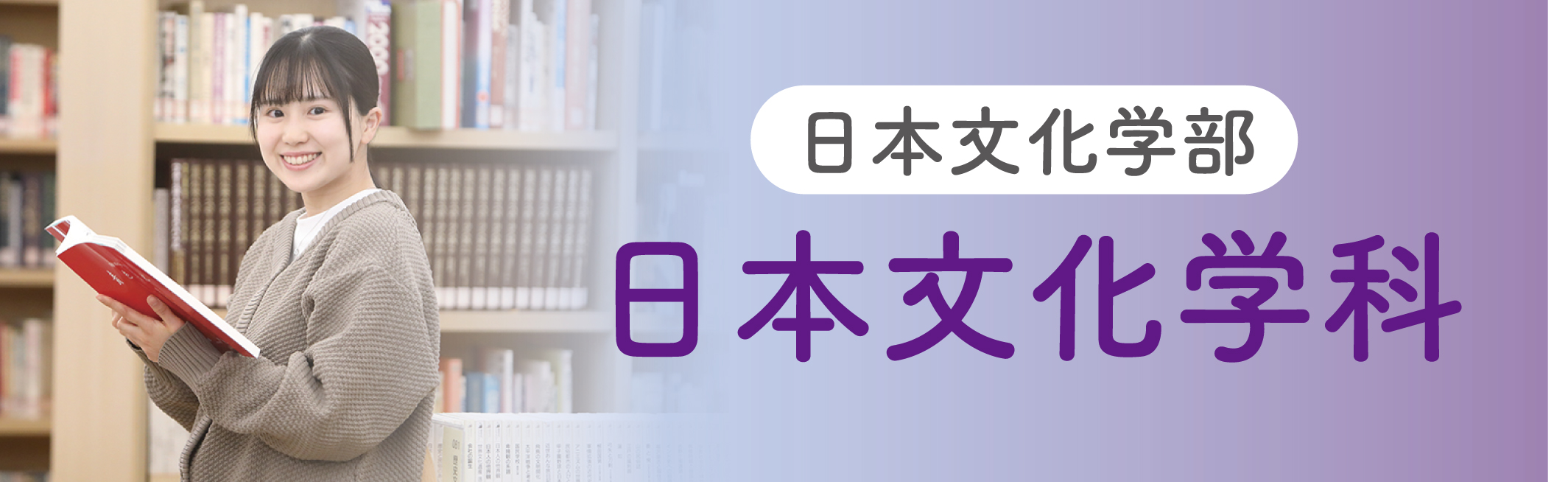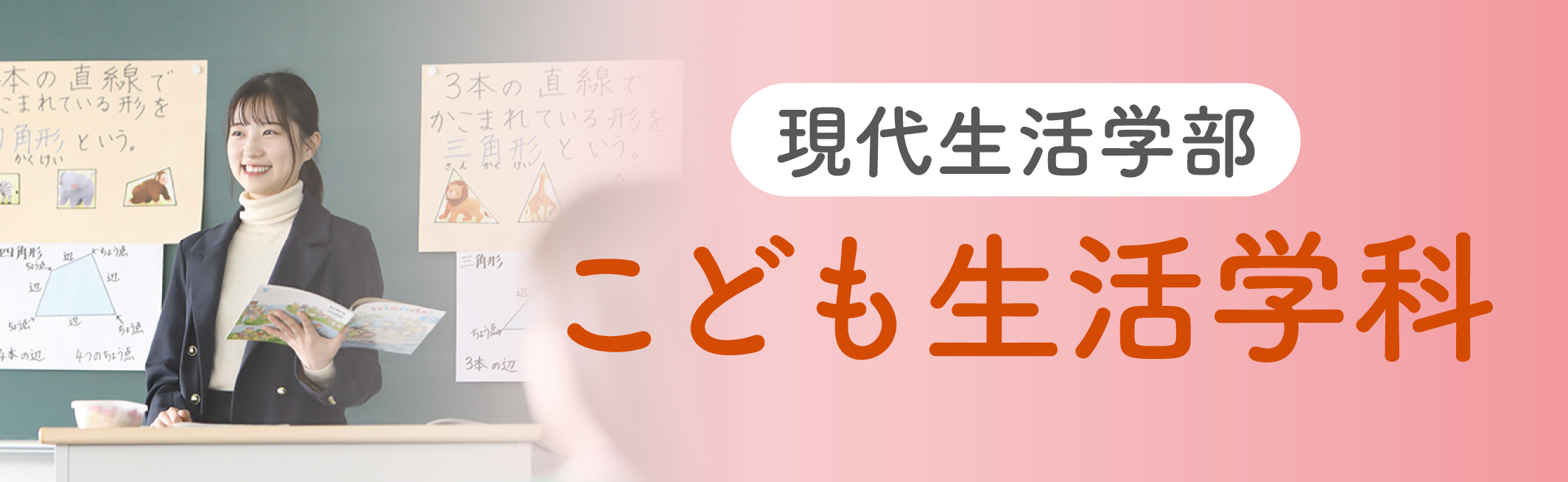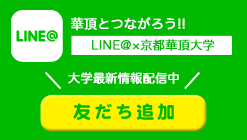教員紹介【橋本 道範 教授】
| 教員名 | 橋本 道範(はしもと みちのり) |
|---|---|
| 職名 | 教授(日本文化学部長) |
| 学歴 | 京都大学大学院文学研究科博士後期課程中退 |
| 学位 | 博士(文学) |
| 担当教科 |
食文化 和食学 総合基礎演習Ⅰ 総合基礎演習Ⅱ 生涯学習論 |
| 専攻・専門分野 | 歴史学・日本中世史・環境史/消費/ナレズシ/淡水魚/生業/村落 |
| 研究テーマ・内容 |
30年にわたり、琵琶湖地域において自然と人間との関係がどう変化していくのかについて研究してきました。特に、フナズシの研究を中心に、淡水魚介類の消費研究を進めています。また、博物館がウエルビーイングにどう貢献するのかについても考えています。
\こういう研究・授業をしています/ 日本の歴史学はながらく「消費」という問題を軽視してきました。そこで、「食」という問題に注目し、日本列島でどのような資源が消費され、独自の「食文化」が形成されていくのかという問題から日本文化の特質を考える授業を行っています。 特に、総合基礎演習、通称「おさかなゼミ」では、淡水魚の食文化を探究します。 |
| 所属学会 |
史学研究会 日本史研究会 史学会 滋賀の食事文化研究会 |
| 学外活動 |
神奈川大学日本常民文化研究所客員研究員(2018年4月~) 日本史研究会編集委員(2015年10月~2017年10月) 日本史研究会研究委員(1992年11月~1993年11月) |
| 研究業績:著書 |
編著『自然・生業・自然観―琵琶湖の地域環境史―』小さ子社 2022年 編著『再考ふなずしの歴史』サンライズ出版 2016年 単著『日本中世の環境と村落』思文閣出版 2015年 |
| 研究業績:論文 |
・「日本産淡水魚消費論―全体史に向けた試み―」歴史学研究1054 2024年 ・「コード化された自然と村落―琵琶湖地域のヨシをめぐって―」歴史学研究1042 2023年 ・「消費論からみた中世菅浦―」史学雑誌129-6 2020年 ・「網野善彦と「自然そのものの「論理」」」歴史評論805 2017年 ・「日本中世における「水辺」の支配―播磨国矢野庄の「河成」をめぐって―」 歴史地理学58-1 2016年 |
| メッセージ |
少子化やグローバル化。日本はいま歴史の大きな転換点にたっています。 都市でも農山漁村でも、これまでの伝統文化を継承するために、新たな創造が求められています。京都を楽しみながら、新しい日本文化を創造する力を華頂で養いましょう。 |